COLUMN
コラムCOLUMN
コラム公開日:2025.04.24
地方自治体の人材不足解消のための課題解決について、現状や要因、取り組み、技術を詳しく解説します。働き方改革や雇用条件改善、AIやRPAの活用など、有効な方法を紹介しています。
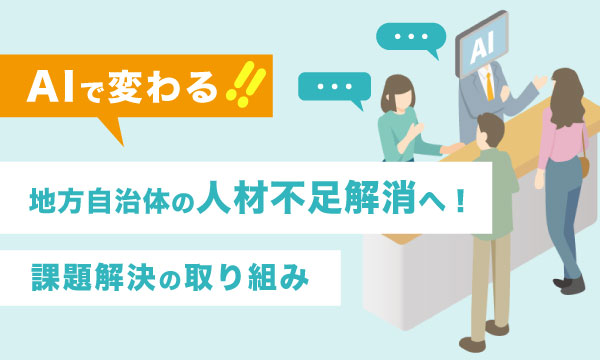
地方自治体での働き手不足は深刻な問題です。人材不足によって行政サービスの質低下や地域課題への対応力低下を招く可能性があります。この記事では、その現状を説明した上で、人材不足になっている要因、どのように解決に取り組むべきかを具体的に解説します。
地方自治体の人材不足がどれほど深刻であるかがわかるだけでなく、自治体が取り組むべき地域課題やDXなどの業務効率化によって、どのように効果的に解決に繋げられるのかが理解できます。また最新技術の導入(AIやRPAなど)が、いかに地方自治体の人材不足解消に役立つかもイメージできるようになるはずです。
【 目次 】
地方自治体の人材不足は深刻な問題であり、行政サービスの提供が困難になりつつあります。その理由は、地方の人口減少や高齢化の進行、若者の都市への流出などが挙げられます。
地方自治体の職員不足によって、地域の問題解決や社会の活性化に対する取り組みが手薄になれば、地方創生が進まない状況になりかねません。これに対応するために、地方自治体や企業がさまざまな取り組みを行っています。
地方自治体の人材確保は、今後の日本の経済や産業、社会の発展にとって重要な課題です。そのため、地方自治体や企業、国の支援が必要です。地方自治体の人材不足解消に向けた努力が求められています。
地方自治体の採用状況は厳しさを増しており、多くの自治体が毎年採用予定人員の枠を設定しているものの、実際には採用できる人材数が不足しています。その一因として、求職者の地方に対する関心が薄れている傾向があることが挙げられます。
また、自治体の給与水準や職場環境が、他の企業と比較して低いことも採用難に拍車をかけています。これにより、地方自治体での採用を検討する求職者が減少し、人材不足の解消が困難になっています。
地方自治体で働く若手職員の離職率が高まっており、これが人材不足に拍車をかけています。若手職員が離職する理由は、キャリアアップの難しさや職場環境が挙げられます。そのため地方自治体では、若手職員に対する教育や研修を充実させ、キャリアアップのサポートや職場環境の整備に力を入れています。しかし、それでも離職率を抑えきれない状況に置かれています。
今後、地方自治体は、若手職員の定着を図るために、働きやすい職場環境の整備やキャリア支援、職員同士のコミュニケーションの促進など、できる限りの対策を講じる必要があります。
自治体が人材不足になる要因は、地域の人口減少や高齢化、経済活動の低迷が原因です。これにより求職者が減少し、固定的な人材が確保できない状況が続いています。また、地方自治体の制度や職場環境が求職者にとって魅力を感じにくいことも人材不足に拍車をかけています。
長時間労働と給与の低さは、地方自治体の雇用条件が民間企業に劣る理由と言われています。職員が働く時間は長く休日も少ない傾向があるとされており、働き手にとってストレスが溜まりやすい環境になりやすいといわれています。
さらに、民間企業と比較して給与も低めに設定されていることが多く、高い労働力を求める一方で、報酬がそれに見合わないことから、若手の人材が離れがちであり、採用や人手不足の課題が深刻化しています。これらの問題は、企業の競争力や地域経済にも悪影響を与えることから、自治体はいかに労働環境を改善し、働きやすい状況を整えるかが重要な課題となっています。
多くの地方自治体の中には、いまだにDX(デジタルトランスフォーメーション)が大きく遅れているところも多い状況です。デジタル社会が当たり前の中で生きてきた若者にとって、働きにくいと感じてしまいます。
現在社会ではIT技術の活用や業務効率化が求められますが、自治体はこうした取り組みが遅れがちで、業務の効率化が進まず働き手に負担がかかります。これは、人材確保や働き手の満足度にも影響し、雇用条件の改善が求められる一因となっています。
地方自治体で習得する技能は、民間企業など他の職場で使えないことが多く、転職のしにくさが課題となっています。近年は転職が当たり前になりつつあり、これがマイナスに働き、魅力的な雇用条件を求める若者たちが他へ流れてしまうのです。自治体の人材難がさらに深刻化し、地方の発展や地域課題の解決に支障をきたすことになります。
地方自治体の職員は、アナログな書類作成など時間がかかる雑務が多く、本来やりたいまちづくりなどの業務に時間が取れません。こうした状況により、働く意欲を持っていた若者もやりがいを感じず、転職を考えるケースが少なくありません。この問題を解決するためには、業務効率化や働く環境の改善が不可欠であり、地方自治体が取り組むべき課題の一つとなっています。
多くの地方自治体は、人材不足の課題に直面しており、その解消に向けたさまざまな取り組みを行っています。これらの取り組みにより、地方の労働環境が向上し、多くの人材が地域企業で働くことが期待されます。今後も地方自治体は、人材不足解消のための積極的な取り組みを継続し、地元企業の成長と繁栄に貢献していくことでしょう。
地方自治体は、働き方改革の推進を通じて、職員の労働環境の改善を図っています。具体的な取り組みとしては、柔軟な勤務制度の導入やテレワークの推奨、労働時間の短縮、残業報酬などが挙げられます。
また、効率的な業務運営のためのITツールの活用や、業務改革によるムダの排除など、労働生産性の向上にも積極的に取り組んでいます。これらの施策により、働きやすい環境が整い、人材が地方自治体に集まりやすくなることが期待されます。
地方自治体では、雇用条件を改善する取り組みも行われています。職員の労働組合からも条件改善の要望が上がることが多く、賃金の見直しや福利厚生の充実を図り、魅力的な雇用環境の整備が議論されています。
また、労働条件に関する情報の公開を積極的に行い、働く人に対して透明性や信頼性を提供しています。さらに、正社員と非正規社員の待遇格差を縮小する取り組みも進められ、働くすべての人に公平な待遇が与えられるよう努めています。
職員のキャリア支援については、地方自治体が役場の外でもサポートしています。たとえば、他の自治体や企業への出向プログラムを通じて、新たな経験やスキルを身につける取り組みが挙げられます。また、大学と連携した研究プログラムに参加することで、専門知識を深める機会を提供しています。さらに、セミナーや研修に積極的に参加する機会を設けることで、職員が自分自身のキャリアをより充実させることが可能になります。これらの取り組みにより、職員自身の成長と地方自治体の人材力の向上が期待されます。
DX(デジタルトランスフォーメーション)やBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)は、企業の業務効率化を実現する手法として認知されています。これらの取り組みには、AI導入など新技術の活用が不可欠です。
たとえばAIは、業務効率化において大きな役割を果たしており、住民からの問い合わせ対応を行いながらディープラーニングを行い、最適な対応に向けた精度向上が続けられています。AI活用の代表例は対話型AIでしょう。AIが住民からの問いかけに対してタイムリーに受け答えを行うことで、これまで職員にかかってきた負担が減り労働時間や人材コストの削減が実現されています。
またAIだけでなく、コールセンターやFAQページの運営を外部に委託することで、職員の人件費よりも安いコストで定型的な業務ができるようになります。
人材不足解消のためには、新技術の活用が重要です。とくにAIやRPA(ロボットプロセスオートメーション)の活用により、労働力を補完し、労働環境を改善することが可能になりつつあります。
RPAは定型的かつ単純な業務を自動化する技術で、多くの企業で導入が進んでいます。RPAの活用により、定型業務に職員の手が取られることが減り、労働時間の短縮や人手不足の解消、労働者の負担軽減など、企業における業務効率化が実現されています。具体的には、保守業務や事務処理の自動化によって、社員がより付加価値の高い仕事に専念できるようになり、生産性が向上します。
AIの活用により、労働力不足の解決が期待できます。たとえば自治体窓口業務に対話型AIを導入することで、窓口対応にかかる業務負荷を軽減し、対応品質の維持・向上、コストダウンを実現できます。AIによるチャットボットや、電話口での自動会話などのサービスが普及し始めています。
今回は、さまざまな方法による人材不足解消の取り組みを紹介しました。とくにAIは、人材不足解消に悩む自治体にとって有効な解決策として注目され、導入が進んでいます。
エイジェックは、2025年4月に対話型AIツール「そうだんAI-Te」をリリースします。労働力不足や人材確保に関する問題を解決し、業務効率化の実現をサポートします。それに先立ちエイジェックは神奈川県海老名市と共同で、対話型AIによる業務効率化や住民の利便性向上などを確かめることを目的に、対話型AIの実証実験を実施しました。実証実験では、利用者の半数以上が50代以上の方となり、50代以上の方にも抵抗なく使っていただけている結果が出ました。実際に、「話すだけなので簡単に利用できる」「AIなので間違ったことを言っても恥ずかしくない」などのお声もいただいており、高齢の利用者が多い地方自治体でも「そうだんAI-Te」は人材不足の解消が充分に期待できることが分かりました。対話型AIに興味を持ってくださった方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
AIが行政窓口を変える!海老名市とエイジェックの実証実験がスタート
https://www.agekke.co.jp/16184/
海老名市:市長定例記者会見資料
市の窓口業務で「対話型生成 AI」を活用した実証実験を開始
~市民のサービスの革新と業務効率化を目指して~
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/611/shiryo1.pdf